日本の和食~天ぷら |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本の和食~天ぷら |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
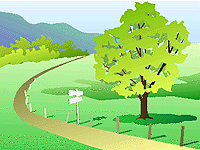 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
| 日本の和食~天婦羅(てんぷら)のページ | |||||||||||||
 |
今や和食には欠かせない存在となっている天ぷら年々増えている外国人観光客からも「食べたい和食」「おいしかった和食」の一つとして常に名前があがる人気の天ぷら料理です。日本を代表する料理といわれる天ぷらですが、「天ぷら」という語感や「小麦粉の衣をつけて油で揚げる」という調理方法は伝統的な和食とは少し違うようです | ||||||||||||
| 「天ぷら」の歴史について | |||||||||||||
| 天ぷらの起源はどこにあるのでしょうか? | |||||||||||||
| 日本に天ぷらの調理法が伝わったのは室町時代鉄砲の伝来とともに"南蛮料理"としてポルトガルから伝わったとされポルトガル語の「テンポーラ(temporas)」「四季に行う斎日」が語源という説があります カトリックでは、四季に行う斎日(テンポーラ)で祈祷と断食を行い、その間は肉食を禁じ代わりに野菜や魚に小麦粉で衣をつけて揚げた料理を食べていたそうです |
|||||||||||||
| 「安土桃山時代」日本の天ぷらの起源とされる「長崎天ぷら」は、それより少し後の安土・桃山時代にポルトガル人が長崎に伝えたといわれています このときの衣は、水を使わずに小麦粉、卵、酒、砂糖、塩を混ぜたもの厚いフリッター状の衣にはしっかりと味が付いており、食材と衣の両方を味わうものでした ただ、その頃の日本では油は大変貴重なものでした。そのため、油を大量に使う天ぷらは高級品であり、庶民の口に入ることは滅多にありませんでした。 |
|||||||||||||
| 「江戸時代初期」になると、油の生産量が増え、天ぷらは江戸の"庶民の味"として徐々に広まっていきました。その当時に発達したのが、日本のファストフードのルーツでもある屋台。寿司、うなぎ、そばなどの屋台とならんで人気のあった天ぷらの立ち食い屋台では、串に刺した天ぷらがおやつ感覚で食べられていたそうです 江戸に広まった江戸天ぷらは、薄い衣で味も風味を残す程度にして、天つゆをつけて食べるスタイルでした。文献に初めて「てんぷら」が登場するのも江戸時代。 1669年の「料理食道記」に「てんぷら」の名称が記されたのが最初ですが、現在の天ぷらと思われる料理法が最初に文献に登場するのは1748年に刊行された「歌仙の組糸」です。 |
|||||||||||||
| ここには「てんふら」の作り方として、「てんふらは、何魚にでも饂飩(うどん)の粉まぶして、油にて揚る也。但前にあるきくの葉てんふら、又牛蒡(ごぼう)、蓮根、長いも其他何にでもてんふらにせんには、饂飩の粉を水醤油とき塗付て揚る也」という記述がありますこの頃には現在とほぼ同じ天ぷらが食べられていたようです。 | |||||||||||||
| 天ぷらの語源は? | |||||||||||||
| 天ぷらの語源にはいくつかの説があります。前述の「テンポーラ(temporas)」のほか、同じくポルトガル語で料理という意味の「テンペーロ(tempero)」が転じたという説 他には天麩羅阿希(あぶらあげ)から、漢字の阿希(あげ)を省いた「天麩羅」から「てんぷら」となったという説もあり、天ぷらの語源については、江戸の戯作者、山東京伝の弟京山が書いた「蜘蛛の糸巻」(1846年)の中にも記されています。 |
|||||||||||||
| 震災(1923年の関東大震災)をきっかけに江戸天婦羅が全国に専門店や料亭が登場 | |||||||||||||
| 庶民の味として屋台料理で広がった天ぷらですが、江戸時代の終わりから明治時代にかけては、天ぷら料理の専門店や料亭が登場し、高級料理としての地位も確立します それとともに、揚げる素材や油の種類、衣にこだわった金ぷらや珍ぷら、銀ぷらなどが出現出前スタイルで材料や道具を持ち込み、客の目の前で天ぷらを揚げる職人(福井扇夫)が話題になるなど、いわゆる「お座敷天ぷら」が生まれたのもこの頃とされています。 また、「江戸の料理だった天ぷら」が日本全国で食べられるようになったのは、大正12年(1923年)に起こった関東大震災がきっかけといわれています 震災で職を失った職人たちが日本各地に移り住み、東西の職人たちが交流することで、東京でも関西風の天ぷら(薩摩揚げ)が食べられるようになり、「江戸天ぷら」も全国に広まりました。 |
|||||||||||||
| 油が高価だった昭和初期、天ぷらは、ハレの日の特別な料理だった | |||||||||||||
| こうして、全国に浸透していった天ぷらですが、昭和初期には油が高価だったことから、お祝いごとや祭りごと、お正月などに食べる特別な料理に。高級天ぷら専門店の「ハゲ天」や銀座「天一」が誕生したのもこの頃です。その後、太平洋戦争の戦時下では、食糧不足のため貴重な油脂を使った料理を楽しむことが困難となり、天ぷらは「贅沢なごちそう」となっていきました。 | |||||||||||||
| 戦後になると家庭料理としても、より身近な存在となった天ぷら | |||||||||||||
| 経済が回復するのに伴い日本の食生活も徐々に豊かになっていきます雑誌やテレビなどの普及によって、多彩な料理情報が消費者に届くようになり、旬の野菜や魚介類などを使ったおいしい天ぷらの情報に注目が集まるようになります。 | |||||||||||||
| 高度経済成長期になると | |||||||||||||
| 食用油脂の生産量増加に伴い、日本人の油や脂肪摂取量が急速に増加油で揚げる料理は家庭でも手軽となり、栄養も豊富な天ぷらは広く食卓に登場するようになりました。それと同時に、スーパーマーケットの惣菜売り場でも天ぷらを中心とした揚げ物が人気となり、惣菜市場も成長していきます。 様々な変遷を経て、世界に誇れる日本の国民食として成長を遂げた天ぷらその魅力が広く認知されていった背景には、「昭和天ぷら粉」の貢献が大きかったのかもしれません。 | |||||||||||||
| 天ぷらを使った料理 | |||||||||||||
| 一般的料理としては、天ぷらを「白飯」にのせ、タレまたは塩味をつけた「天丼」や「天重」、かけ蕎麦・うどんにのせた「天ぷら蕎麦」「天ぷらうどん」、天ぷらと蕎麦を別々にした「天もり」「天ざる」「天せいろ」も一般的な料理であり、多くの蕎麦屋では丼類、麺類それぞれの最高級メニューとして花形を飾っている。 天ぷらを「卵」でとじた「天とじ」もある。 関東地方では、天ぷら蕎麦から蕎麦を抜いた「天ぬき」を提供する店も多い 他には、天ぷら(かき揚げ)を「茶漬け」にした「天茶」や、名古屋などには天ぷらを「おむすび」でくるんだ「天むす」もある広島県尾道市や岡山県、岐阜県、青森県、北海道などでは、「ラーメン」の具「天ぷらラーメン、天中華」としても提供される。 「大衆食堂」や弁当」のメニューとしても多くみられ、ご飯と共に食べる日本においては一般的な食べ物である |
|||||||||||||
| 調理法 |  |
||||||||||||
| 食材は下粉を打って(小麦粉をまぶして)から「衣液」に浸し、深い鍋(天ぷら鍋)を使用し多量の熱い油(160-180℃程度)で揚げることによって調理を行う。 「華を咲かせる」とは揚げ終わったときに衣が広がって食感をよくさせることであり、この技法が使用されることがある揚がった天ぷらは、天ぷら鍋に取り付けた「天ぷら網」あるいは「天台(天ぷらバット)」などに移して油を切る中華鍋を代用する場合もある。 |
|||||||||||||
| 衣とは | |||||||||||||
| 一般的に、衣液は「鶏卵」「冷水」「小麦粉」は(薄力粉)で作る 小麦粉は軽く数回サックリと混ぜる程度にして、グルテン生成を抑えるグルテンは天ぷらの揚げ上がりの食感を悪くするからであるグルテンにより衣に粘りが出てしまうことを「足が出る」というグルテン生成の少ない、製粉後しばらく期間を置いた小麦粉を使うこともある。 一方、でん粉や米粉やベーキングパウダー(膨らし粉)などが加えられた「天ぷら粉」が業務用も家庭用も市販されている天ぷらはかつては高い調理技術が求められ、家庭料理と料理人の作品には明らかに差が見て取れる難しい料理と考えられてきたが、ミックス粉の開発・普及により、素人でも気軽に作れる料理に変わりつつある。紫蘇の葉、山芋、抹茶、道明寺粉、ウニ、あられ、細かく切った春雨・蕎麦・素麺などを用いた変わり衣も用いられることがある |
|||||||||||||
| 花とは | |||||||||||||
| 衣を散らせるように揚げることを「花を咲かせる」などと呼ぶ、揚げている通常の天ぷらに衣の元を箸などで散らすことで衣を増やす一般的に技術を要するとされる | |||||||||||||
| 揚げ油は | |||||||||||||
| 揚げ油は天ぷらの香りを決定付ける重要な要素である。 「ごま油」または「綿実油」を使用し独自に配合した揚げ油を使用する天ぷら店もある ごま油を使用すると衣がこんがりと色が付く「黒天ぷら」、サラダ油などを使用すると衣が白っぽい「白天ぷら」になる。他にも「椿油、オリーブオイルや大豆油」もなど様々な植物油を用いられる 屋台料理としての天ぷらは、高温のごま油で揚げた黒天ぷらが主流であったが、お座敷天ぷらは白くさっくりと揚がる「太白油」(非焙煎のごま油)を用いられ差別化が図られた 江戸時代はごま油が高価であり、これが原因で天ぷらが庶民の口に入りづらく、天ぷらは高級な料理であった。この後、安価な「なたね油」の使用により天ぷらが庶民にまで普及が加速した経緯もある 第2次世界大戦後の沖縄県では、物資不足の時代、食用油の代わりに「機械油」が用いられたこともあった「モービル天ぷら)」現在では「食用油」が安価に入手できるためにわざわざ機械油を食用にもちいることはない また、日本本土でも揚げ油に「ひまし油」が使用された例があり、風味は決して悪くないと主張する利用者も存在したものの、消化不良で、体調を崩したり、あるいは下痢に陥ったりした者もあったとされる。植物や鯨油などの動物由来の機械油なら食用の可能性はなくはないが、中には人体で消化できない油や、ひまし油のように確実に有害な油もあり、さらに石油由来の鉱物油の場合人体への重大な悪影響が考えられ、利用に耐え得る食材とは言えない。 「食用油」は空気に触れると酸化して変質する油は数回の料理の後に適度に交換する方が良い 使用後はなるべく空気に触れない状態で冷蔵庫で保存する |
|||||||||||||
| 使用後の揚げの処理 | |||||||||||||
| 西洋風のとフライ料理と同じく、天ぷらも廃油が残る。自治体は、水質汚染など生態系への悪影響は下水道の詰まりを避けるため、廃油を排水口に流さないよう指導している このため廃油を固化させて捨てやすくする凝固剤が市販されている このほか、「地球温暖化対策」としての「二酸化炭素(CO2)」排出抑制のため、業務用(飲食店や惣菜工場)に使われた大量の廃油は回収されて、持続可能な「航空燃料(SAF)」を含むバイオ燃料の材料として利用される廃油もある |
|||||||||||||
| タネとは |  |
||||||||||||
| ウド、タラの芽、ナス(茄子)などのアクのある野菜でも薄衣にしたり片面衣にしたりするなどして100℃以上の高温にさらすことで、えぐみや苦みが出にくくなる。但し、色の変化を防ぐために前処理する場合があることと、高温にさらすことがアクのある野菜全てに有効なわけではない。 江戸前天ぷらでは、新鮮な車えび、穴子、はぜ、きす、白魚、青柳、ぎんぽなどを主に「ごま油」で揚げる。 油で揚げている最中にタネの温度が上がり急上昇すると、共に水分や空気を遮断する 油中にあるため、衣に閉じ込められた空気や水分・水蒸気が衣を破ったり油を跳ねさせりすることがあるそのため、尾のついた海老を天ぷらとする際に、尾の先端を切り中に含まれる水分を抜くといった下処理を行うこともある。 また、仕上りを美しくするために、タネに「隠し庖丁」を入れたり「筋切り」をすることがある 高温の調理で硬くなるもの(蛤や烏賊などは薄く切ったり、切れ目を入れたり、あらかじめ軽く湯がいたりするといった「下拵え」によって、衣も種も適度に揚がるように「仕事」をすることもある タネの名に「天」を付し「海老天」「ナス天」などと呼ばれることもある また、芝海老や小柱などの細かく切り刻んだ、あるいは元から細かい野菜類や魚介類を衣と混ぜ合わせて揚げたものは「かき揚げ」と呼ぶこともある 江戸時代の「守貞漫稿」に「蕎麦屋の天ぷら」は「芝海老」だったと書かれており、かき揚げも天ぷらと呼び、天ぷら屋のメニューである。 「青海苔」を入れた衣を使ったものや、「板海苔」をタネに巻いたもの、あるいは板海苔に衣を付けて揚げたもの(衣を種の片面だけに付けることもある)は「磯辺揚げ」(いそべあげ)とも呼ぶ。タネとしては穴子、鱚、海老、イカなどの魚介類、茄子、蓮根、南瓜などが代表的であるが、これらに限定されず種々の魚介類や野菜に加えて、季節の「山菜」や「きのこ」など様々な食材を用いる。ちくわなどの練り物を使う場合もある。 一部地域では「鶏肉」を使った「とり天」(鶏天・鳥天)、かしわ天といったバリエーションもある。 「牛肉や豚肉」を揚げた料理は「肉天」「豚天」と呼ばれる。肉の場合「天」と付いていても、 調味料で下味を付けたり、衣に「片栗粉」を使ったりする「から揚げ」に近い調理法もある |
|||||||||||||
| 盛り付けは | |||||||||||||
| 皿の上に、余分な油を吸う「天紙を敷いて」盛り付けられることが多い その際に乱雑に盛るのではなく、盛り付け方にも拘られることがある 敷紙を半分に折る場合、紙を傾けて折られることがあるが、「懐紙」のマナーとして紙の左下を上に持っていく折り方(上にかぶさる紙の元々底だった辺が右肩下がりになる)だと祝儀、反対に(紙の右下を上に持っていく折り方(同左肩下がり)だと不祝儀の折り方とされ、後者の折り方は避けられることがある敷紙を折るとわずかに空間があき油を吸い込みやすくなり、また敷紙を折ることは染みた油が直接皿などに付くと敷紙が透けて見た目が悪くなるのも防いでいる。 |
|||||||||||||
| 食べ方は |  |
||||||||||||
| 江戸時代の屋台では現在の大阪の串カツのように、串に刺した天ぷらを共用の「つゆ」につけ、「大根おろし」と共に食べていた当時の江戸の「つゆ」は現在の天つゆに比べてかなり甘辛く濃いものであったようで、それを丼飯に載せた早飯として「天丼」が誕生したといわれている 現在でも東日本では家庭料理としては「醤油」をつけて食べることもありまた「ぬれ天ぷら」と称して客に出される以前から甘辛いタレを含ませその味で食べさせる例もある 一方、近畿地方では「だし汁」(天つゆ)で食べる文化が発達し、現在の日本では天ぷらを単品として食べる場合は薄味の天つゆと共に供するのが一般的とされる。これは近代以降、特に関東大震災を契機として東西の食文化の交流が起こった結果であり、現在は東京の天ぷら専門店でも揚がった天ぷらは天皿、天つゆは(呑水z(とんすい)に入れて供される 天つゆは「出汁」と「味醂」と「醤油」と「砂糖」が基本となるつけ汁で「大根おろし、紅葉おろし、おろし生姜、柚子、山椒」などが「薬味」として用いられる。 食材によっては「塩」や「柑橘類」の絞り汁で食べることもある。 塩は粗塩や岩塩などの他、(抹茶(抹茶塩・茶塩)、「カレー粉」(カレー塩)、柚子皮(柚子塩)、山椒」「トリュフ」を混ぜた物も使用される 西日本、特に和歌山県や沖縄県などでは「ウスターソース」をかけて食べることも一般的である |
|||||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||