日本の四季~冬 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本の四季~冬 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
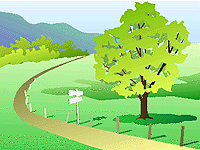 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
| 日本の四季「冬」についてのページ |
|||||||||||||
| ◇この暦に記載されている~用語の解説 旧暦について 月の朔望と潮回り(潮名・干満時刻)について 九星について 雑節について 六輝・六曜(ろっき・ろくよう)について 干支(えと)・十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)について 日本の年中行事について 七五三について 五節供について 二十四節気について 選日について 年末年始について 国民の祝日と休日について 便利な和暦・西暦早見表 |
|||||||||||||
| 区分 | 古代中国 | 現在(西欧流) | 慣習的 | 細分した自然季節区分(日本) | |||||||||
| 冬 | 立冬から立春の前日まで | 冬至から春分の前日まで | 12月・1月・2月 | ・初冬(11月26日~12月25日) ・冬(12月26日~1月31日) ・晩冬(2月1日~2月28日) |
|||||||||
| ・立冬(りっとう)11月7日頃 立冬とは、冬の始まりという意味です。太陽の光が弱まり冬枯れの景色が目立つようになります。 季語は、「冬立つ」「冬入る」などを用います全国の学校では文化祭が行われる時期です。 ・冬至(とうじ)12月22日頃 冬至は「日短きこと至(きわまる)」という意味です。日短きこと至るとは一年で一番太陽が出ている時間が短い日ということです別の言い方をすると、この日は一年で最も夜の時間が長いということになります。そのために、昔の人は生命が終わる時間だと考えていたようです。現在でも、その厄を払うためにかぼちゃやお汁粉を食べ体を温めることで、栄養を取り無病息災を願う習慣が続いています。 |
|||||||||||||
| 二十四節気について | |||||||||||||
| 二十四節気とは、節分を基準に1年を24等分して約15日ごとに分けた季節の事で、1か月の前半を「節」後半を「中」と言います。その区分点となる日に季節を表すのにふさわしい春・夏・秋・冬等の名称を付けました。12個の中気と12個の節気の総称で、中国の戦国時代に成立した。節気ないし二十四機とも略称する。二十四節気は現在季節の区切りとして受け取られているがその名称は今から二千何百年も昔の華北の気候に基づいて名付けられたものであるから、日本の気候と合わないものがあっても不思議ではない。 | |||||||||||||
| 節気(せっき)1カ月の前半 | 中気(ちゅうき)1カ月の後半 | ||||||||||||
| 節気とは立春・啓蟄・立夏と立春から一つおきにとったものを言う。 | 中気とは暦月の名称を決めるのであるから正月雨水は正月に2月春分は4月にあるのが原則である。中気は暦法上、閏月を定めるためには大切な役割があり節気より重視される一般の人にとっては節気の方がはるかに関心がもたれ、そのことは古い仮名暦では中気は記載されずただ<せつ>と節気のみが記された例が多い | ||||||||||||
| 節気(せっき) <1ヶ月の前半> |
中気(ちゅうき) <1ヶ月の後半> | ||||||||||||
| 冬 | ・立冬(りっとう)11月7日頃 立冬とは、冬の始まりという意味です。太陽の光が弱まり冬枯れの景色が目立つようになります。季語は、「冬立つ」「冬入る」などを用います全国の学校では文化祭が行われる時期です。 ・大雪(たいせつ)12月7日頃 大雪とは、山岳ばかりでなく平野にも雪が降り積もる季節ということから付いた呼び名です。この頃になると九州地方でも氷が張ります。街はクリスマスの飾りでにぎやかになるころです ・小寒(しょうかん)1月5日頃 小寒は「寒の入り」つまり寒さの始まりという意味です。本格的な寒さではないという意味があるようですが、実際はこの頃になると寒さは厳しくなります寒中見舞いは小寒から出し始めます |
冬 | ・小雪(しょうせつ)11月22日頃 小雪とは、冬とはいえまだ雪はさほど多くないという意味です。冬将軍が到来すると言われる時期ですので北の地方ではコタツを押し入れから出す家が増える頃なのではないでしょうか。西日本においては夏ミカンを収穫する季節に入ります。 ・冬至(とうじ)12月22日頃 冬至は「日短きこと至(きわまる)」という 意味です。日短きこと至るとは一年で一番太陽が出ている時間が短い日ということです別の言い方をすると、この日は一年で最も夜の時間が長いということになります。そのために、昔の人は生命が終わる時間だと考えていたようです。現在でも、その厄を払うためにかぼちゃやお汁粉を食べ体を温めることで、栄養を取り無病息災を願う習慣が続いています。 ・大寒(たいかん)1月20日頃 大寒とは、一年で最も寒い時期という意味です小寒から数えて15日後とされており、小寒から大寒までの15日間と大寒から立春までの15日間の合計30日間を「寒の内」と言います。耐寒のため様々な行事が行われます。寒気を利用した食べ物(氷豆腐・寒天・酒・味噌など)を仕込む時期にも当たります。 |
||||||||||
| ◇この暦に記載されている~用語の解説 旧暦について 月の朔望と潮回り(潮名・干満時刻)について 九星について 雑節について 六輝・六曜(ろっき・ろくよう)について 干支(えと)・十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)について 日本の年中行事について 七五三について 五節供について 二十四節気について 選日について 年末年始について 国民の祝日と休日について 便利な和暦・西暦早見表 |
|||||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||