暦~十干・十二支・干支について |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
暦~十干・十二支・干支について |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
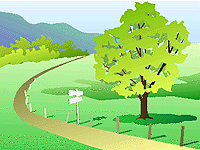 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
| 十干(じっかん)・十二支(じゅうにし) ・干支(えと)についてのページ |
|||||||||||||
| ◇この暦に記載されている~用語の解説 旧暦について 月の朔望と潮回り(潮名・干満時刻)について 九星について 雑節について 六輝・六曜(ろっき・ろくよう)について 干支(えと)・十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)について 日本の年中行事について 七五三について 五節供について 二十四節気について 選日について 年末年始について 国民の祝日と休日について 便利な和暦・西暦早見表 |
|||||||||||||
| ・干支は、読み方は「えと」 別表記は「かんし」 ・干支とは、古代中国を発祥とする、時間や方角の数え方であり、その単位である。 ・十干は陰陽五行思想のエレメントである木・火・土・金・水をそれぞれ陰陽(「え」と「と」)の両性質に分けた10要素からなる。 |
|||||||||||||
| 十干(じっかん) | |||||||||||||
| 甲(きのえ) | 乙(きのと) | 丙(ひのえ) | 丁(ひのと) | 戊(つちのえ) | |||||||||
| 己(つちのと) | 庚(かのえ) | 辛(かのと) | 壬(みずのえ) | 癸(みずのと) | |||||||||
| 十二支は12項目からなる。(訓読み) | |||||||||||||
| 現代日本においては「今年は寅年」とか「酉年生まれです」とかいう場合に「干支」(えと)が参照される、その意味で干支に接する機会はまだ残っているが、これは正確にいえば「十二支」であって「干支」ではない。十干十二支のうち、十干をはぶいて、十二支だけで表した年をいう。子年・丑年・寅年などと。 十二支は➡子(ね・ねずみ)令和2年(2020)➡丑(うし)令和3年(2021) ➡寅(とら)令和4年(2022)➡卯(う)令和5年(2023)➡辰(たつ)令和6年(2024) ➡巳(み・へび)令和7年(2025)➡午(うま)令和8年(2026)➡未(ひつじ)令和9年(2027) ➡申(さる)令和10年(2028)➡酉(とり)令和11年(2029)➡戌(いぬ)令和12年(2030) ➡亥(い・いのしし)令和13年(2031)となります。 |
|||||||||||||
| 十二支 (じゅうにし) |
由来など | ||||||||||||
 |
子(ね・ねずみ)・音読み:し・訓読み:ね ・ねずみの繁殖力はとても強く、子孫繁栄財力の象徴とされていました。 |
||||||||||||
| 丑(うし) ・音読み:ちゅう・訓読み:うし ・牛は、乳や肉など大事な食料であり、古来より人間と深く馴染のある家畜でした。 |
|||||||||||||
 |
寅(とら)・音読み:いん・訓読み:とら ・寅は、はるか昔から恐れられる動物として神秘的な存在でした。 |
||||||||||||
 |
卯(う)・音読み:ぼう・訓読み:う ・兎は、家族で行動するため家族愛を象徴する動物とされていました。 |
||||||||||||
| 辰(たつ)・音読み:しん・訓読み:たつ ・伝説の生き物である龍は、古来より高貴の象徴とされていました。 |
|||||||||||||
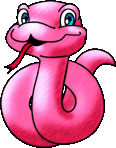 |
巳(み・へび)・音読み:し・訓読み:み ・蛇は、お金に縁の深い生き物とされ、多産と豊穣をあらわすとされました。 |
||||||||||||
 |
午(うま)・音読み:ご・訓読み:うま ・馬は、家畜、労働力として役に立ち、牛同様人間とのかかわりが深い動物でした。 |
||||||||||||
| 未(ひつじ)
・音読み:び・訓読み:ひつじ ・羊も牛や馬などとならび人間との付き合いが深い動物でした。 |
|||||||||||||
 |
申(さる)・音読み:しん・訓読み:さる ・人間の祖先として、古来から大切にされていました。 |
||||||||||||
 |
酉(とり)・音読み:ゆう・訓読み:とり ・鶏は、人間に時を知らせる生き物として大切にされていました。 |
||||||||||||
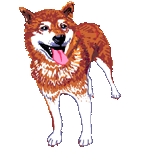 |
戌(いぬ) ・犬は、人間に最も忠実とされ人間と深く結びついていました。 |
||||||||||||
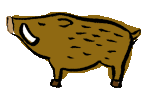 |
亥(い・いのしし)
・音読み:がい・訓読み:い ・猪の肉は、万病に効く食べ物として信じられ無病息災の象徴でした。 |
||||||||||||
| 干支(えと) | |||||||||||||
| 干支は「十干」と「十二支」の組み合わせにより構成されており、全60項からなる。「十干」は甲・乙・丙・丁~と続く項目群であり、「十二支」は子・丑・寅・卯~と続く項目群である。 毎年、年が変わるごとに1つずつこの干支が廻り、60年経つと1周します。60歳を迎える際に「還暦」といいますが、これは60歳になって生まれた年の干支に戻るので、暦が えと[0] [干、支] 「え(兄)おと(弟)の略 ・十干と十二支とを組み合わせたもの。木・火・土・金・水の五行を、それぞれの陽の気を表す「え」と陰の気を表す「と」とに分けたものが十干、 甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)。これに十二支、すなわち、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)を順に割り当て、甲子(きのえね)・乙丑(きのとうし)のように呼ぶ。これで六〇の組み合わせができる。年月・時刻・方位などを表す呼称として用いられる。 |
|||||||||||||
| 干支(えと)の例:甲子(きのえね)の組み合わせは、甲(きのえ)と子(ね) | |||||||||||||
| 干支番号1~30番 | 干支(えと) | 干支番号31~60番 | 干支(えと) | ||||||||||
| 干支番号1番目 | 甲子・・・きのえね | 干支番号31番目 | 甲午・・・きのえねうま | ||||||||||
| 干支番号2番目 | 乙丑・・・きのとうし | 干支番号32番目 | 乙未・・・きのとひつじ | ||||||||||
| 干支番号3番目 | 丙寅・・・ひのえとら | 干支番号33番目 | 丙申・・・ひのえさる | ||||||||||
| 干支番号4番目 | 丁卯・・・ひのとう | 干支番号34番目 | 丁酉 ・・・ひのととり | ||||||||||
| 干支番号5番目 | 戊辰・・・つちのえたつ | 干支番号35番目 | 戊戌・・・つちのえいぬ | ||||||||||
| 干支番号6番目 | 己巳・・・つちのとみ | 干支番号36番目 | 己亥・・・つちのとい | ||||||||||
| 干支番号7番目 | 庚午・・・かのえうま | 干支番号37番目 | 庚子・・・かのえね | ||||||||||
| 干支番号8番目 | 辛未・・・かのとひつじ | 干支番号38番目 | 辛丑・・・かのとうし | ||||||||||
| 干支番号9番目 | 壬申・・・みずのえさる | 干支番号39番目 | 壬寅・・・みずのえとら | ||||||||||
| 干支番号10番目 | 癸酉・・・みずのととり | 干支番号40番目 | 癸卯・・・みずのとう | ||||||||||
| 干支番号11番目 | 甲戌・・・きのえいぬ | 干支番号41番目 | 甲辰・・・きのえねたつ | ||||||||||
| 干支番号12番目 | 乙亥・・・きのとい | 干支番号42番目 | 乙巳・・・きのとみ | ||||||||||
| 干支番号13番目 | 丙子・・・ひのえね | 干支番号43番目 | 丙午・・・ひのえうま | ||||||||||
| 干支番号14番目 | 丁丑・・・ひのとうし | 干支番号44番目 | 丁未・・・ひのとひつじ | ||||||||||
| 干支番号15番目 | 戊寅・・・つちのえとら | 干支番号45番目 | 戊申・・・つちのえさる | ||||||||||
| 干支番号16番目 | 己卯・・・つちのとう | 干支番号46番目 | 己酉・・・つちのととり | ||||||||||
| 干支番号17番目 | 庚辰・・・かのえたつ | 干支番号47番目 | 庚戌・・・かのえいぬ | ||||||||||
| 干支番号18番目 | 辛巳・・・かのとみ | 干支番号48番目 | 辛亥・・・かのとい | ||||||||||
| 干支番号19番目 | 壬午・・・みずのえうま | 干支番号49番目 | 壬子・・・みずのえね | ||||||||||
| 干支番号20番目 | 癸未・・・みずのとひつじ | 干支番号50番目 | 癸丑・・・みずのとう | ||||||||||
| 干支番号21番目 | 甲申・・・きのえさる | 干支番号51番目 | 甲寅・・・きのえねとら | ||||||||||
| 干支番号22番目 | 乙酉・・・きのととり | 干支番号52番目 | 乙卯 ・・・きのとう | ||||||||||
| 干支番号23番目 | 丙戌・・・ひのえいぬ | 干支番号53番目 | 丙辰・・・ひのえたつ | ||||||||||
| 干支番号24番目 | 丁亥・・・ひのとい | 干支番号54番目 | 丁巳・・・ひのとみ | ||||||||||
| 干支番号25番目 | 戊子・・・つちのえね | 干支番号55番目 | 戊午・・・つちのえうま | ||||||||||
| 干支番号26番目 | 己丑・・・つちのとうし | 干支番号56番目 | 己未・・・つちのとひつじ | ||||||||||
| 干支番号27番目 | 庚寅・・・かのえとら | 干支番号57番目 | 庚申・・・かのえさる | ||||||||||
| 干支番号28番目 | 辛卯 ・・・かのとう | 干支番号58番目 | 辛酉・・・かのととり | ||||||||||
| 干支番号29番目 | 壬辰・・・みずのえたつ | 干支番号59番目 | 壬戌・・・みずのえいぬ | ||||||||||
| 干支番号30番目 | 癸巳・・・みずのとみ | 干支番号60番目 | 癸亥・・・みずのとい | ||||||||||
| ◇この暦に記載されている~用語の解説 旧暦について 月の朔望と潮回り(潮名・干満時刻)について 九星について 雑節について 六輝・六曜(ろっき・ろくよう)について 干支(えと)・十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)について 日本の年中行事について 七五三について 五節供について 二十四節気について 選日について 年末年始について 国民の祝日と休日について 便利な和暦・西暦早見表 |
|||||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||