節分の日〜恵方巻 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
節分の日〜恵方巻 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
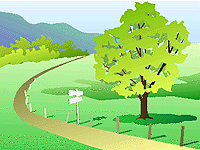 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
| 節分の日〜恵方巻のページ | |||||||||||||
| 「節分」とは、前の季節が終わって次の季節に変わる、「節」を「分」ける日のこと節分「せちわかれ」とも言います。つまり、現在広く知られている立春の前日だけが節分なのではなく、立夏の前日、立秋の前日、立冬の前日も節分の日であり、かつてはこれらの日(年4回)に、その季節で溜まった穢れを祓うための節分行事が行なわれていたのです。やがて、もっとも重要な季節である立春前日の節分だけが年中行事として残り、今でも各地の有力神社では、大がかりな節分の行事が行なわれています。 | |||||||||||||
| ◎節分には何をするのか | |||||||||||||
○豆まき
*豆を投げる理由・・・「追儺(ついな)」とは、災厄をもたらす悪霊・邪気を追い払う行事です |
|||||||||||||
| ○恵方巻(えほうまき)きを食べると縁起が良いとされる。大阪を中心とした風習。 恵方(吉方位)をその年の歳徳神(としとくじん)の位置する方角「恵方」に向かって巻き寿司を無言で丸かぶりする *巻き寿司には、「福を巻き込む」という願いがこめられ、切らずに食べるのは「縁を切らない」という意味があります。 |
|||||||||||||
| 太巻きの作り方(4本分) | |||||||||||||
 |
 |
♪材料(4本分) ①米・3カップ②水・3カップ③寿司酢・90cc④ほうれん草・1/2束 ⑤さくらでんぶ・大さじ2⑥三つ葉・適量⑦焼きのり・4枚⑧かんぴよう・20g |
♪調味料ほか ⑨水・2カップ⑩上白糖・大さじ4⑪しょうゆ・大さじ2 ⑫たまご・4個⑬上白糖・大さじ2⑭塩・少々⑮味の素・少々 ⑯サラダ油・適量 |
||||||||||
 |
♪そのほか(下拵えなど) ①米は炊く30分前にといでザルにあげます。水を加えて普通に炊きます。 ②炊き上がったらご飯をバットに入れ、寿司酢を回しかけて、 手早くあおぎながらしゃもじで切るように混ぜて、寿司飯を作ります。 ③かんぴょうは塩少量でもみ、洗って水気を絞り鍋に入れます。 上白糖、醤油を加え、煮立ったらアクを取り弱火で汁気がなくなるまで煮ます。 ④卵は溶きほぐして、上白糖、塩、味の素を混ぜ合わせます。 フライパンにサラダ油を熱して玉子焼きを作ります。 巻きすで形を整えて細長く切ります。 ⑤ほうれん草はさっと塩茹でして食べやすい大きさに切ります。 |
||||||||||||
| ♪巻き方 ①巻きすを広げてのりをのせます。 上2cmほどあけて寿司飯を1/4量を広げ、その上に具材をのせます。 ②具材を包むように一気に一巻きししっかり押さえます。 ③切らずに盛りつけます。 |
|||||||||||||
| ♪恵方巻の食べ方 ①恵方巻(えほうまき)きを食べると縁起が良いとされる。 大阪を中心とした風習 ②恵方(吉方位)をその年の歳徳神(としとくじん)の位置する方角「恵方」に 向かって巻き寿司を無言で丸かぶりする ③関西発祥の行事。2012年の恵方は北北西! ④巻き寿司には、「福を巻き込む」という願いがこめられ、切らずに食べるのは 「縁を切らない」という意味があります。 |
|||||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||