日本三大奇祭〜御柱祭 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本三大奇祭〜御柱祭 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 |
|||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
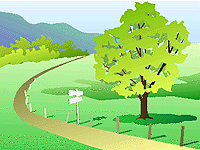 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
〜御柱祭(長野県)のページ |
|||||||||||||
| 開催日:七年に一度の寅と申の年 *お出かけ前にご確認ください |
|||||||||||||
| ○信州・諏訪大社では七年に一度の寅と甲の年に宝殿を新築し、社殿の四隅にあるモミの大木を建て替えるまつりを行います。 ○この祭りを「式年造営御柱大祭」、通称「御柱祭」と呼び、諏訪地方の6市町村21万人の氏子がこぞって参加する天下の大祭です。 ○祭神として建御名方神と八坂刀売神を祀り、東国第一の軍神として坂上田村麻呂や源頼朝、武田信玄、徳川家康らの崇敬を集めました。現在では全国に1万社以上の分社があるといわれています。 ○祭りでは、長さ約17m、直径1m余り、重さ10トンを超える巨木を山から切り出し、人力のみで各神社までの道中を曳いて、最後に社殿を囲むように四隅に建てます。 ○ 柱を山から里へと曳き出す「山出し」→4月に神社までの道中を曳きます ○御柱を各社殿四隅に建てる「里曳き」→5月に上社・下社それぞれで行われます。 |
|||||||||||||
| 諏訪大社は上社と下社に分かれる諏訪市に上社本宮、茅野市に上社前宮があり、下諏訪町に下社春宮と下社秋宮があります。中でも上社本宮は最も観光客が多く、人気のある神社です | |||||||||||||
| 上社本宮 | 上社前宮 | 下社秋宮 | 下社春宮 | ||||||||||
 |
 |
 |
 |
||||||||||
| 綱置場に置かれた8本の御柱は茅野市宮川にある御柱屋敷まで11.9kmの道程を氏子らにより曳行される。 道中、難所の木落し、川越しがある | |||||||||||||
上社の木落とし |
上社の川越し |
||||||||||||
| 曳行は注連掛(しめかけ)まで4.7km。道中、萩倉地区を過ぎた地点で最大難所、木落し坂にぶつかる曳行は注連掛(しめかけ)から春宮が1.7km、秋宮までが3.1km。道中の下諏訪町内は騎馬行列や長持ちなどで賑わう。春宮、秋宮の社殿四隅に4本の御柱が建てられフィナーレとなる。 | |||||||||||||
下社の木落とし |
里曳き |
||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||