日本の三大祭り |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本の三大祭り |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
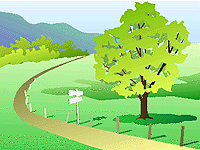 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
| 日本の三大祭りのページ | |||||||||||||
詳しい、日時、場所等はホームページなどでご確認の上、お出かけください |
|||||||||||||
| 人がいて人々が集まって、町ができる。そこにはみんなの「願い」や「祈り」が生まれる。「豊作」「大漁」「無病息災」「商売繁盛」「学業成就」「恋愛」「安産」とそれらの対象に日本人は「神様」を祀ってきました。「神様」に感謝して日本人は「お祭り」を催してきました。日本には様々な所に「神様」がいます。私たちはその時の「願い」によって拝み奉ってきた。「神様」がいる代表的な場所が神社です。誰でも神社に初詣に行ったことがあると思います。 | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 神田祭 (5月)東京都 ・神田明神  |
◆神田祭の変遷 ・神田祭は、西暦730年の神田明神創建から数えて約1280年続く祭りで、西暦1603年、徳川幕府が江戸に開かれて以降盛んに行われる。 ・明治時代に入り、不景気と電線架線などの影響から、明治22年を境に山車が出されなくなっていった ・大正時代に入ると山車がほとんどなくなり、神社の神輿が渡御する「神輿渡御祭」へと変化 ・昭和に入り、震災後、何度か渡御祭は延期されたが、昭和5年に復活・戦後昭和27年祭りの名称を渡御祭から神幸祭に変更し、初の神幸祭が斎行この時は、一の宮の鳳輦のみで牛が曳く形式だった。・昭和40年代になると交通事情のため、5月中旬に行っていた神幸祭を祝日の5月2・3日に改定。・昭和50年、三越から奉納された二の宮の神輿が行列に追加。 ・昭和59年に平将門の三の宮鳳輦が新調、昭和62年行列に加わる ・平成に入り、諌鼓鶏の山車の復活、将門武者行列などを始めとするさまざまな神賑行事を行い今日に至る。 |
||||||||||||
| 祇園祭 (7月)京都市 ・八坂神社  |
◆祇園祭(ぎおんまつり)は、京都市東山区の八坂神社(祇園社)の祭礼で、明治までは「祇園御霊会(御霊会)と呼ばれた。 ・貞観年間(9世紀)より続く。京都の夏の風物詩で、7月1日から1ヶ月間にわたって行われる長い祭りである。 ・祭行事は、八坂神社が主催されるものと山鉾町が主催するものに大別される。一般的には山鉾町が主催する行事が「祇園祭」と認識されることが多く、その中のハイライトとなる山鉾行事だけが重要無形文化財に指定されている。 ・山鉾が設置される時期により前祭(さきまつり)7月14日〜16日と後祭(あとまつり)7月21日〜23日の二つに分けられる。 ・山鉾巡業は、前祭7月17日後祭7月24日が著名である。八坂神社主催の神事は、「神輿渡御」(神幸7月17日・還幸7月24日)や神輿洗7月10日・7月28日が著名で、「花傘連合会」が主催する花傘巡業(7月24日)も八坂神社側の行事と言える。 ・祇園祭は数々の日本の三大祭りに挙げられる京都の三大祭・日本三大祭・日本三大曳山祭・日本三大美祭等日本を代表する祭り。 |
||||||||||||
| 天神祭 (7月)大阪市 ・大阪天満宮  |
◆天神祭(てんじんまつり、てんじんさい)は、日本各地の天神宮(天神社)で催される祭り。祭神の菅原道真の命日にちなんだ縁日で25日前後に行われる ・一年のうち1月の初天神祭などある月に盛大に行われることがある。 ・各神社で行われる天神祭の中では、大阪天満宮を中心とし大阪市で行われる天神祭が有名である。 ・天神祭は、日本三大祭(京都の祇園祭、東京の神田祭)の一つ。 ・又、生國魂神社の生玉夏祭、住吉大社の住吉祭と共に大阪三大夏祭り期間は6月下旬吉日7月25日の約1ヶ月間に亘り諸行事が行われる。 ・特に25日の本宮の夜は、大川(旧淀川)に多くの船が行き交う船渡御(ふなぎょ)が行われ、奉納花火があがる。他に鉾流神事(ほこながししんじ)、陸渡御(りくとぎょ)などの神事が行われる。24日宵宮、25日本宮。 |
||||||||||||
| |
|||||||||||||
| 山王祭 (6月) 東京都・日枝神社 |
祇園祭 (7月) 京都市・八坂神社 |
天神祭 (7月) 大阪市・大阪天満宮 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 祇園祭 (7月)京都市・八坂神社 |
博多祇園山笠 (7月)福岡市 |
会津田島祇園祭 (7月)福島県 ・田出宇賀神社・熊野神社 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 神田囃子 (5月)東京都・神田神社 |
祇園祭 (7月)京都市・八坂神社 |
花輪ばやし (8月)秋田県・幸稲荷神社 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 帆手まつり (3月)宮城県・塩竃神社  |
灘のけんか祭り (10月)兵庫県 ・松原八幡神社  |
北条祭り (10月)愛媛県・鹿島神社  |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 西大寺会陽 (2月)岡山市・西大寺  |
筥崎宮の玉取祭 (1月)福岡市・筥崎宮  |
古川祭起し太鼓 (4月)岐阜県  国府宮の裸祭り (2月)愛知県  |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 飯坂けんかまつり (10月)福島県 |
新居浜太鼓祭り (10月)愛媛県 ・一宮神社  |
岸和田だんじり祭り (9月)大阪府 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 祇園祭 (7月)京都市・八坂神社 |
春の高山祭(山王祭) 4月岐阜県・日枝神社  |
秩父夜祭 (12月)埼玉県・秩父神社 秋の高山祭(八幡祭) 10月岐阜県・桜山八幡神社 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| なまはげ柴灯まつり (2月)秋田県・真山神社  |
御柱祭 (4月)長野県・諏訪地方  |
吉田の火祭り (8月)山梨県・冨士浅間神社  |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 御田植祭 (4月)千葉県・香取神宮 |
伊雑宮御田植祭 (6月)三重県 ・伊雑宮御料田 |
御田植神事 (6月)大阪府・住吉大社  |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 長崎くんち (10月)長崎県・諏訪大社 |
博多おくんち (10月)福岡市 ・櫛田神社 |
唐津くんち (10月)佐賀県・唐津神社 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 昆沙門天大祭 (2月)静岡県 ・昆沙門天妙法寺  |
七草大祭だるま市 (1月)群馬県 ・少林山達磨寺  |
深大寺だるま市 (3月)東京都・深大寺  |
|||||||||||
| 尾張津島天王祭り (7月)愛知県・天王川公園 |
竿燈まつり(8月)秋田県 |
二本松ちょうちん祭り (10月)福島県・二本松神社 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 山形花笠祭り (8月)山形県  |
群上おどり (8月)岐阜県  |
阿波おどり (8月)徳島市  |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 西馬音内の盆踊り (8月)秋田県  |
群上おどり (8月)岐阜県 |
阿波おどり (8月)徳島市 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 黒石よされ (8月)青森県  |
群上おどり (8月)岐阜県 |
阿波おどり (8月)徳島市 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 土浦全国花火競技大会 (10月)茨城県 |
全国花火競技大会 (8月)秋田県  |
長岡まつり花火大会 (8月)新潟県 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||
| 湘南ひらつか七夕まつり (7月)神奈川県  |
仙台七夕まつり (8月)宮城県  |
一宮七夕まつり (7月)愛知県  |
|||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||