日本三大提灯祭〜尾張津島天王祭り |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本三大提灯祭〜尾張津島天王祭り |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
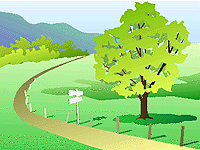 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
〜尾張津島天王祭り(愛知県)のページ |
|||||||||||||
| 開催日:7月第四土曜日 *お出かけ前にご確認ください |
|||||||||||||
| 津島神社 | |||||||||||||
 |
全国に三千有余あるといわれる天王社の総社である。 津島須佐之男命を祭神として,古くより尾張天王社として知られています「津島の天王様」「津島さん」と呼ばれ,疫病や厄難除けの神様として全国から崇敬されています.歴代尾張国主となった織田・豊臣徳川氏の崇敬も厚く,現在の本殿は清須城主だった松平忠吉(家康四男)の寄進で,楼門とともに桃山様式を今に伝える建物です。(重要文化財指定) |
||||||||||||
| 津島天王祭りは,7月第4土日に津島神社と天王川公園で繰り広げる大祭で,一般に津島川祭り津島祭とも呼ばれます.一般的に知られる神葭(みよし)神事と車楽による川祭りが中心。その「宵祭」と「朝祭」を紹介します | |||||||||||||
| 宵祭は、天王川に浮かぶ津島五車のまきわら船の提灯に灯がともされると、 宵祭の始まりです。 |
|||||||||||||
| 宵祭りは津島五車の車楽(だんじり=朝祭りの車楽と区別して巻藁船・提灯船とも呼びます)が提灯を飾り車河戸と天王川の御旅所を往復します 巻藁舟二隻の舟を繋ぎその中心に真柱を立てて、ここに12個(1年12月を象徴.閏年は13個)の提灯をかかげます。半円形に一年の日数三百六十五個(実際は約400個)の提灯を付けますその他なべづる・軒提灯・燈籠・高張提灯・弓張提灯・箱提灯など数多くの提灯で装われます.その他の提灯も合計すると、一隻あたり五百五十程度の提灯がつく事となる。それが五隻なので、一回の祭りで最低でも二千七百五十個の提灯とロウソクを使用し、点灯する順番で、三種類の大きさがある。真柱と坊主の下側は一番大きく、五百五十個の提灯が最後まで灯っているようになっている。午後7時頃から,これらの提灯に点火され,やがて5艘の巻藁船は提灯の灯を水面に映しながら川を遡り,御旅所に到着します.花火もあがり,津島祭りのクライマックスです |
|||||||||||||
| 宵祭りを終えて車河戸に帰る車楽は, 当番車の合図により,航行しながら一斉に朝の車楽へと飾り替えを競い合う |
|||||||||||||
巻藁船・提灯船とも呼びます |
半円形400個の提灯 |
花火もあがり, 津島祭りのクライマックスです  |
|||||||||||
| 朝祭は、市江車を先頭に6艘の車楽舟が能の出し物をかたどった置物を飾り、 楽を奏でながら漕ぎ進みます |
|||||||||||||
| 朝祭は津島の五隻に、佐屋町市江地区の「市江車」が先頭に加わる。市江車には十人の若者が締め込み姿で布鉾を持ち、途中から天王川に飛び込み泳ぎ、津島神社に通じる岸まで渡る。その後、神社まで走って神前に布鉾を奉納する。舟(車楽舟)の最高部には、能装束を模してつくられた衣装をまとった人形が乗るが、津島の五隻中、先頭を行く当番車には必ず「高砂」が乗る。 その他の四隻は毎年能番組が変わり毎年の楽しみの一つでもある。文献では、織田信長が津島によく来ており、津島祭りも当時の天王橋の上から見物をしたという記録も残っている。他にも、大事な行事の一つに「神葭(みよし)流し」がある。朝祭の終了後の深夜、社殿に奉斎されていた古い神葭を天王川に流すものだ。新しい神葭は津島神社本殿に納められ、一年間人々の祈願を受ける。 |
|||||||||||||
 |
二隻の舟をつなぎ |
真柱に12個の提灯 |
|||||||||||
| 朝祭りの山車 津島の五隻に、佐屋町市江地区の「市江車」が先頭に加わる。 | |||||||||||||
| 市江車 | 今車 | 筏場車 | 下車 | 堤下車 | 米車 | ||||||||
| 市江島 | 今市場 | 筏場 | 下構 | 堤下 | 米之座 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||