日本三大祇園祭〜会津田島祇園祭 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本三大祇園祭〜会津田島祇園祭 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
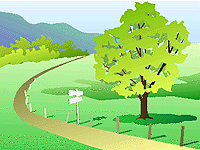 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
〜会津田島祇園祭(福島県)のページ |
|||||||||||||
| 開催日:7月22日〜24日 *お出かけ前にご確認ください |
|||||||||||||
| 今から400年前の慶長8年に、領主長沼盛実が京都八坂神社に準じた祭礼格礼を取り入れ、「祭の決まり」を定めて、現在の祇園祭に至ったとされています。 祇園信仰は疫病から守ってもらう祈りや、自分たちの元にこないように祓ってもらう信仰です。 伊達政宗が会津を支配した時代に、一時、祭は出来なくなりましたが、祭礼を定めた慶長8年に住民が当時の城代小倉作左衛門(じょうだいおぐらさくざえもん)にお願いして、祭が再興されました。 当時は、天王祭と呼んで6月15日に行われていたようです。 明治4年、天王社は田出宇賀神社に合祀となり、田出宇賀神社例祭が祇園祭と合併の祭日となりました。 更には熊野神社の例祭日が明治12年に同一日になるなど、様々な改変を重ねてきましたが、祇園祭の伝統は、牛頭天王奉鎮以来の社家である現宮司室井家により、脈々と今に伝わり、その礼式が保持されています。 このように、現在の祭礼の形態は |
|||||||||||||
| 田出宇賀神社拝殿内部は向かって左が熊野神社、右が田出宇賀神社と二神社奉っています。 (社殿の前の御賽銭箱も二つ。) 後年、熊野神社も祇園祭に加わり、熊野神社の三行器を合わせて現在では七行器が十行器となりました。 |
|||||||||||||
| 下の写真左が熊野神社、右が田出宇賀神社 | |||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 行事のタイムスケジュール | |||||||||||||
| 7月22日 宵祭 | 7月23日 本祭 | ||||||||||||
| ◆オープニングセレモニー:正午 ◆江戸下町職人展:12時〜22時30分 ◆子供歌舞伎通し上演(予定):13時前後 ◆子供歌舞伎屋台上演:16時〜22時30分 ◆大屋台運行:16時〜22時30分 |
◆七度の使い:7時頃 ◆七行器行列:7時30分〜8時頃 ◆江戸下町職人展:8時〜23時頃 ◆神輿渡御〜還御:10時30分〜14時頃 ◆子供歌舞伎屋台上演:16時〜23時頃 ◆大屋台運行:16時〜23時頃 |
||||||||||||
| 7月24日 太々御神楽祭 | |||||||||||||
◆大々御神楽:13時〜15時 |
|||||||||||||
| ◆大屋台運行:16時〜22時30分 | |||||||||||||
| 頃祇園祭で運行される屋台は4つありそれぞれの地区にちなんで、西屋台・上屋台・中屋台・本屋台と呼ばれています各屋台には、芸場と呼ばれる場所で子供歌舞伎を上演するほか、運行中は子供たちを乗せ勇壮に駆けていきます。喧嘩屋台とも呼ばれる迫力ある屋台の駆け引きは、世話人と呼ばれる男性たちの屋台に懸ける意気込みを表しています | |||||||||||||
| ◆大屋台運行:16時〜23時頃 | |||||||||||||
| ◆大々御神楽:13時〜15時 祭りのクライマックスである。24日に神社の神楽殿で奉納される終始無言の神楽舞です。この太々御神楽が終わると、一年がかりで続いた祇園祭全ての行事が、神社、党屋、屋台共に終わりを告げます。 |
|||||||||||||
| ◆七行器行列:7時30分〜8時頃 | |||||||||||||
 |
七行器行列は氏子から神前にお供え物を献上する神聖な行列です七つの「行器」(ほかい)には、お神酒をいれた「角樽」が3つ、赤飯を入れた足のついた「行器」が3つ、それに鯖を載せた「魚台」(うおだい)が1つです。行器は、裃姿の男性、花嫁姿の女性により、捧げ持ちされ献上されます。毎年、40人前後の花嫁さんが列を成して歩く姿は豪華絢爛で、神事の厳かな印象をホッとするやさしい印象で包んでくれます。 | ||||||||||||
| アクセス ●車:宇都宮ICから今市経由で91kmのR121号沿い。 又は西那須野ICからR400号塩原・上三依経由56kmのR121号沿い。 ●電車: 東武鉄道浅草駅から会津鬼怒川経由3時間15分。会津田島駅 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||