日本三大祭〜春の神田祭 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
日本三大祭〜春の神田祭 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 |
|||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
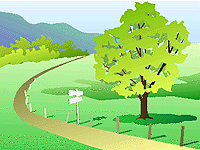 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
〜春の神田祭(東京都)のページ |
|||||||||||||
| 開催日:5月7日()〜日() (開催時間は各日により異なります) *お出かけ前にご確認ください |
|||||||||||||
| 神田祭は京都、祇園祭と大阪、天神祭とならんで日本3大祭として豪華爛漫な祭礼を江戸中を繰り広げて来ました。また、浅草神社の三社祭と日枝神社の山王祭とともに東京三大祭の一つでもあります。西暦の奇数年の5月に行われるお祭りです | |||||||||||||
| ◆神田祭の変遷 | |||||||||||||
| ・神田祭は、西暦730年の神田明神創建から数えて約1280年続く祭りで、西暦1603年、徳川幕府が江戸に開かれて以降盛んに行われるようになった。 ・明治時代に入り、多数の山車が出されるなど盛大な祭礼が行われた時もあったが、不景気と電線架線などの影響から、明治22年を境に山車が出されなくなっていった。また、明治25年の神田祭から、台風、疫病流行の時期を避けるため、祭月を9月→5月に変更。以降、今日まで5月に行われている。 ・大正時代に入ると山車が出されることは殆どなくなり、神社の神輿が渡御する「神輿渡御祭」へと変化 ・大正8年、2基の神輿を鳳輦(ほうれん)1基に改めた(この鳳輦は大正12年の関東大震災により焼失)。震災後、何度か渡御祭は延期されたが、昭和5年に復活。渡御祭の行列では一の宮仮鳳輦(御羽車)と二の宮神輿が渡御した。 ・戦後昭和27年、祭りの名称を渡御祭から神幸祭に変更し、初の神幸祭が斎行。 この時は、一の宮の鳳輦のみで牛が曳く形式だった。 ・昭和40年代になると交通事情のため、5月中旬に行っていた神幸祭を祝日の5月2・3日に改定。 ・昭和50年、三越から奉納された二の宮の神輿が行列に追加。 ・昭和59年には平将門の三の宮鳳輦が新調され、昭和62年から行列に加わった ・平成に入り、諌鼓鶏の山車の復活、将門武者行列などを始めとする様々な神賑行事を行い今日に至る |
|||||||||||||
| 本殿から三柱の御祭神の御神霊(みたま)を鳳輦・神輿に遷す。 この厳かな神事によって、神田祭が始まる |
|||||||||||||
  神幸祭  |
 |
 |
|||||||||||
| ◆神田祭にちなんだグッズいろいろ | |||||||||||||
 |
 |
 |
 |
||||||||||
 |
 |
 |
 |
||||||||||
| ◆スケジュール | |||||||||||||
 |
5月7日19時=鳳輦・神輿遷座祭白装束を身に着けた神職により、本殿から三柱の御祭神の御神霊(みたま)を鳳輦・神輿に遷す。この厳かな神事によって、神田祭が始まる。 | ||||||||||||
 |
5月8日夕=氏子町会神輿神霊入れ氏子各町会の神酒所には、揃いの半纏・浴衣に身を拵えた氏子が参列神職の奉仕による神事、御神霊が108氏子、約200基の神輿に遷る | ||||||||||||
 |
5月9日=神幸祭 午前5時過ぎ、「御鍵渡しの儀」(みかぎわたしのぎ)」が鳳輦 ・神輿奉安庫前で行われ、3基の鳳輦・神輿が社殿前に登場し飾り付けが行われる。午前8時、神幸祭行列参加者が参列する中神事が執り行わた後行列がスタート。 神田・日本橋・大手・丸の内 ・秋葉原の約30キロの道のり夕刻に神田明神に帰還 |
||||||||||||
 |
5月10日=神輿宮入神田明神宮入参拝を目指し、 100基近い数の神輿が各連合 ・町会の出発地に集合。式典後に宮入巡行神輿渡御となり、徐々に熱気と興奮が高まる一方、秋葉原中央通りでは、宮入参拝を済ませた神輿が、神輿降り(神輿を振り動かすこと |
||||||||||||
 |
5月14日=献茶式、明神能昭和37年(1962)から始まった表 千家家元の奉仕による古式ゆかしい献茶式。お家元自ら奉仕の見事なふくささばきがご神前で披露される一方の明神能は、平成15年から復活(有料B席3,000円〜) |
||||||||||||
 |
5月15日=例大祭1年で最も重要な儀式で、 毎年五月十五日に斎行される儀式。氏子各町代表参列のもと日本の平和と安全そして氏子の幸せを祈念する。 |
||||||||||||
| ●アクセス他 ・場所:神田神社、神田・日本橋地区周辺 ・所在地:東京都千代田区外神田2-16-2(神田神社) ・お問い合わせ先 03-3254-0753 ・アクセス JR中央線・総武線御茶ノ水駅聖橋口より徒歩5分 JR山手線・京浜東北線電気街口・東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、 東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅聖橋口より徒歩5分 東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩5分 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||