5月の旬の魚 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
| 今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||
5月の旬の魚 |
|||||||||||||
| 日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
| 桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
 |
 |
 |
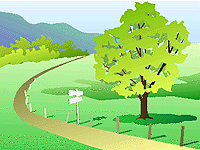 |
 |
 |
 |
|||||||
| 四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
| 旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| ≪日本の文化いろいろ≫ | |||||||||||||
| 5月(春)~旬の魚のページ | |||||||||||||
| およそ3ヶ月ごとに変わる四季「春・夏・秋・冬」の海産物を食としても楽しめ恵まれています | |||||||||||||
| 魚の旬とは? ・魚の味には脂肪の量が大事なポイントになります ・魚の脂肪が一番多くなるのは、産卵期前の、 エサをたっぷり食べて栄養をつけている時です ・この時を魚の旬といいます |
栄養価は 旬の魚~お肉に負けない良い蛋白質 ・食べて頭が良くなる働きと効果のDHA ・血管のそうじをしてくれる働きと効果のEPA |
||||||||||||
| 旬の魚について➜ 旬の魚月別索引→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
| 旬の魚 | 特徴 | ||||||||||||
| 飛魚 (とびうお) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
・トビウオは筋肉質で脂肪が少なく、高タンパクな魚で味は淡白旬は、初夏から夏。小骨の多い魚だが、脂肪分が少なく淡白な味で、塩焼き、フライ等にして食べる。新鮮なものは刺身が美味。トビウオを原料とした竹輪は「あごちくわ」と呼ばれ、鳥取県・兵庫県の特産。島根県では、野焼き(アゴと呼ばれる。竹輪に似るも製法の異なる食べ物があり特産品。新島や八丈島ではくさやに加工される。房総半島の郷土料理「なめろう」の材料にもなる | ||||||||||||
| 西日本では、各地では天日や機械で乾燥処理した「アゴ干し」が作られる。アゴ干し自体や、それを破砕した「トビ節」・炭火やガスコンロなどで焦がした「焼きアゴ」が味噌汁や料理のだしをとるために使われることが多い。山形県飛鳥でも同様に、天日干しと炭火による「焼き干し」が作られており、酒田のラーメンでは、ほとんどがトビウオでダシを取っている。九州北部等では、トビウオのダシ入りつゆで麺が多く食べられ、長崎県や福岡県の醤油メーカーが「あごだし」を商品名に冠した粉末だし・めんつゆ・だしパックを商品化している。マスコミによるPR等で知られるようになった五島うどん(長崎県南松浦郡新上五島町でつくられる郷土料理)も、あごだしを使って食べるうどんである。長崎県平戸市では、あごだしによるラーメンも評判を呼びつつある。なお、トビウオの卵はトビッコと呼ばれ、、珍味や寿司ネタになる | |||||||||||||
| 鱚(きす) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
旬は5月~6月。アオギス、シロギスの2種類、シロギスの方が美味しい三枚におろして刺身にしたり、天ぷらや酢の物、塩焼き、すし種、汁の実にすると美味しい。白身の身肉は淡白な味で、脂肪が少なく、タンパク質や鉄分が豊富に含まれている | ||||||||||||
山女(やまめ) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
ヤマメは山奥の清流に住む魚で、天然物の旬は解禁日以降の3月~4月。 香りは薄いが、淡白な味は川魚でもトップクラスで、塩焼き煮付け、寒露煮などにする。市場に出回るのはほとんどが養殖ヤマメ |
||||||||||||
| 石持(いしもち) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
生鮮魚介類の流通過程において「いしもち」といった場合は「シログチ」を指すのが一般的である。晩春から夏にかけての魚で、産卵期の5月が一番味がよい。卵だけ煮付けたりもする。身は淡白で柔らかいので、濃い目に煮付けたり、空揚げ、揚げ煮などがよく合う | ||||||||||||
鰈(かれい) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
カレイの旬は種類によって異なり、1年中食べられる。マコガレイ、イシガレイは初夏。マガレイは秋から冬.。ヤナギムシカレイは春 ・カレイの逸品、城下ガレイは4月~8月が美味しい。 ・カレイは脂肪が少なくあっさりした淡白な味で、タンパク質を多く含む。歯、骨、血液、筋などの重要な構成成分であるリンを多量に含んでいる。 ・カレイの種類はいろいろありますが、一般的に料理にするのは「真がれい」「真子がれい」「石がれい」など身の大きいもの。「笹がれい」など小さい物は干物に向いています。 ・おいしさだけでなくかれいのタンパク質は消化が良く、ビタミンB1、B2が多いタンパク質の代謝を早め、胃腸の負担を減らします ・また皮の部分にはお肌に良いコラーゲンが含まれています |
||||||||||||
伊佐木(いさき) 写真クリック ・レシピいろいろ 美味しい時期5月 |
5~6月の産卵期のものは「麦わらいさき」と呼ばれ、脂がのって最も味が良い。クセのない淡白な味だが、磯魚特有の臭みがあり、鮮度が落ちやすい大ぶりで新鮮なものは刺身やあらいに、小ぶりの物は塩焼きなどが良い | ||||||||||||
| 魚の栄養素と効能について | |||||||||||||
| 必須脂肪酸 | |||||||||||||
| 私たちの健康や美容に欠かせない重要な成分であるため、必須脂肪酸と呼ばれています。必須脂肪酸(ひっすしぼうさん)は、体内で他の脂肪酸から合成できないために摂取する必要がある脂肪酸です。人及びその他の動物にとっては、多価不飽和脂肪酸のうち、ω-6脂肪酸のリノール酸、ω-3脂肪酸のα-リノレン酸が必須脂肪酸であり必要量が定められる。 | |||||||||||||
| 脂肪には一般的には3つのタイプがあります | |||||||||||||
| 脂 肪 酸 |
①一価不飽和脂肪酸 | 水素原子のペアが一つ失われている形の脂肪酸です常温で液体です。オリーブオイルやサフラワー油に多く含まれています。 | 栄 養 所 要 量 バ ラ ン ス |
40% | |||||||||
| ②多価不飽和脂肪酸 | 水素原子のペアが2つ以上失われている形の脂肪酸です室温では柔らかい状態になっているか、液体状になっています。大豆油、ひまわり油等に多く含まれています魚の脂肪は主に多可不飽和脂肪酸です。 | 30% | |||||||||||
| ③飽和脂肪酸 | 全ての水素原子が互いに結合している(飽和している)形の脂肪酸です。動物性脂肪は飽和酸が多く、肉、鶏、バターなどの多く含まれています。常温で固まっていますパーム核油、ココナッツ油は飽和脂肪酸が多い。 | 30% | |||||||||||
| 主な魚の脂肪酸比較(五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から) | |||||||||||||
栄養成分
|
単位 |
鰻
|
鮪
|
秋刀魚
|
鯖
|
太刀魚
|
鰤
|
鰆
|
鯵
|
鰯
|
鰹
|
||
白焼き |
生 |
生 |
秋獲生 |
生 |
焼き |
生 |
生 |
生 |
秋獲生 |
||||
飽和脂肪酸 |
g |
6.59 |
5.79 |
4.23 |
4.31 |
5.83 |
3.98 |
2.14 |
2.16 |
3.84 |
0.25 |
||
| 一価不飽和脂肪酸 |
g |
11.95 |
11.27 |
10.44
|
10.29 |
7.26 |
5.17 |
3.26 |
3.07 |
2.80 |
0.29 |
||
多価不飽和脂肪酸和 |
g |
3.10 |
5.63 |
4.58 |
6.76 |
3.87 |
4.52 |
2.30 |
1.89 |
3.81 |
0.19 |
||
|
|
|
みなみ
|
|
大西洋
|
|
成魚 |
|
大西洋
|
ま
|
||||
| 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)脂肪酸成分表編」参考 *魚名クリックで栄養価と効能・料理レシピへ | |||||||||||||
| DHA/EPAを多く含む魚 | |||||||||||||
| 魚名 | DHA量(㎎) | EPA量(㎎) | 目安として | ||||||||||
・鮪(まぐろ)脂身 |
3,200 |
1,400 |
厚生労働省が発表した n-3系脂肪酸の1日の摂取目安量は、 男性は、2.4g、女性は2.0g、 (但し50~69歳の場合となっています。) 1日の摂取目安量の参考として ①刺身なら ・鮪トロで2~3切れ ・ぶりで4~5切れ ②焼き魚なら ・秋刀魚で約1尾 ・小型鰯で約2尾 ③缶詰なら ・鯖水煮缶190g ・鰯の蒲焼缶100g |
||||||||||
・鰤(ぶり) |
1,700 |
940 |
|||||||||||
・秋刀魚(さんま) |
1,600 |
850 |
|||||||||||
・太刀魚(たちうお) |
1,400 |
970 |
|||||||||||
・鰻(うなぎ)養殖 |
1,100 |
580 |
|||||||||||
・鰆(さわら) |
1,100 |
340 |
|||||||||||
・鯖(さば) |
970 |
690 |
|||||||||||
・鰹(かつお)秋獲り |
970 |
400 |
|||||||||||
・魳(かます) |
940 |
340 |
|||||||||||
・鰯(いわし) |
870 |
780 |
|||||||||||
・金目鯛(きんめだい) |
870 |
270 |
|||||||||||
| DHAとEPAの働きと効果 | |||||||||||||
虚血性心疾患」や「脳血管疾患」など身近で日々改善して欲しいような症状にも効果を発揮してくれるとなれば「DHA]「EPA]を含むお魚類をも食べてみようと思いませんか?
|
|||||||||||||
| 強く元気な身体をつくるお魚の栄養 | |||||||||||||
| お魚の部位別の栄養価 | |||||||||||||
| ・ヒレ、 ・魚皮膚や筋肉をつくる ・ヒレにコラーゲンを含む。 ・コラーゲンは 美肌を造る栄養素 ・かの楊貴妃も好んで 食したという 「フカヒレのスープ」があげられます。 |
・筋隔(きんかく)とは、 ・魚の筋肉を縁取っている 白い筋 ・魚に含まれるカルシウムのほとんどがこの部分に集まっています |
・頭と目のまわり、 ・魚好きが絶対見逃さない美味しさ くちびるの肉、頬肉、目玉と目玉のまわりの肉など、小さな肉ながら大変美味しい。 ・血管や皮膚をしなやかにする多糖体やビタミンAが豊富です。 ・目の裏側には「かっけ」予防に効果のある ビタミンB1や脳の成長や発達に関係するDHAが含まれています。 ・頭が美味しい魚、鯛、甘鯛、伊佐木、鰤、鮭な |
|||||||||||
| ・血合肉(ちあいにく)、 ・ビタミン類と鉄が豊富に含まれる。 ・貧血予防に最適な部位。 ・鰹の血合い肉にはたんぱく質 を主成分に、鉄、ビタミンA、 B1、B2,B12、タウリンを 多く含みます。中でもビタミンB1は多く、肉の数十倍も含まれています |
 |
・身、 ・高たんぱく、高脂肪でEPA・DHAを含む ・優血圧やコレステロール値を下げるタウリンを豊富に含む。(鯛、鰈、鱈)また、動脈硬化 ・癌・ぼけなどをはじめとする生活習慣病予防に有効なタウリン、鉄を含みます。 ・肉には含まれていないビタミン類が豊富な部位です |
|||||||||||
| ・内臓、 ・新鮮な魚の内臓にはビタミン類がいっぱい。内臓は脂肪が多く、濃厚な味です。 ・魚に含まれるカルシウムを上手く働かせるビタミンD。 粘膜の健康を保つビタミンAが大量に含まれる |
・皮、 ・肉の部分よりビタミン類が豊富 ・ビタミンAは粘膜の健康を保つ ・ビタミンB2は、糖質代謝に重要な働き。 (特に黒い皮の魚)ほかに ・煮こごりを作るゼラチン質も含みます。 |
・骨、 ・カルシウムが豊富。 ・ビタミンDと一緒に摂る。 ・骨や歯の材料になり、神経 ・筋肉の機能を維持し、神経の興奮を鎮めるなど重要な働きをします |
|||||||||||
| ・魚卵、 ・親より栄養価が高い魚の卵。 ・各栄養素をバランスよく、しかも高濃度に含み、特にビタミンA、ビタミンB群、ビタミンE、ミネラルの銅、亜鉛と身体の目、肌、髪、胃腸、血管などの健康を促進します |
・養殖魚には、 天然魚よりDHAとEPAが沢山含まれています。 ・天然ブリ 37g→養殖ブリ 45g ・天然真鯛 14g→養殖真鯛 28g (100g当たりの含有量) |
||||||||||||
| 魚は身体をつくる栄養が豊冨 | |||||||||||||
| ・DHA (ドコサヘキサエン酸) 頭が良くなりたい(DHA)は認知症の予防、改善効果、緑茶(カテキン)と一緒にとるとさらに効果アップします |
・EPA (エイコサペンタエン酸) 血管の脂肪やコレステロールが気になるそれならEPAです。 |
||||||||||||
| ・タウリン 目に良く、成人病にも。 |
 |
・カルシウム 骨や歯を丈夫にする |
|||||||||||
| ・ビタミン 最近肌にニキビが健康的な肌を保ち美しい肌を保つ ビタミン、動脈硬化や癌を引き起こす悪玉活性酸素 を抑制するビタミンが豊富です。 |
・たんぱく質 強い体をつくりたい、身体の働きを良くするたんぱく質が豊富です |
||||||||||||
旬の魚について➜ 旬の魚月別索引→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
| 〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
| Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
| 【PR】 | |||||||||||||