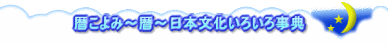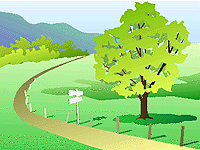およそ
の月齢 |
月の
出る数 |
主な名称 |
|
| 0 |
1 |
朔(さく)
又は 新月(しんげつ) |
月が太陽と同じ方角になり、全くみえない。朔(さく)は天文上の名称。 |
| 2 |
3 |
三日月(みかづき)
若月(わかづき)
眉月(まゆづき)
蛾眉(がび) |
夕方西空に見える細い月。古来信仰の対象だった。蛾眉とは、蛾の触角のように細長く曲がってくっきりと目立つ、美人の眉のこと。 |
| 3日前後 |
|
夕月(ゆうづき) |
夕方見える月のことで、三日月を指すことが多い。 |
| 7 |
|
七日月(なのかづき)
弦月(ゆみはり) |
上弦の月。 |
| 12 |
13 |
十三夜月
(じゅうさんやづき)
後の月(のちのつき)
栗名月(くりめいげつ)
豆名月(まめめいげつ) |
満月の夜の二日前の月で,満月の次に美しいとされてきた後の月・豆名月・栗名月は,十三夜月の中でも特に陰暦9月13日の月を呼ぶ。 |
| 3 |
14 |
十四日月
(じゅうよっかづき)
小望月(こもちづき) |
満月前夜の月。 |
| 14 |
15 |
十五夜(じゅうごや)
満月(まんげつ)
望月(もちづき)
三五の月(さんごのつき)
中秋の名月
ちゅうしゅうのめいげつ)
芋名月(いもめいげつ)
望(ぼう) |
月が太陽の反対側にあり、月に影が無く丸く見える。新月から数えてだいたい15日目あたり。三五の月は、3×5=15(十五夜)からくる言葉遊び。十五夜の中でも陰暦8月15日の月は、中秋の名月又は芋名月という。陰暦では7月〜9月が秋とされたため、8月はその真ん中となり「中秋」と呼ばれた。 |
| 1 |
2 |
二夜の月
(ふたよのつき) |
名月とされた,陰暦8月15日と9月13日の月。二夜の月のうち片方だけを見ることは,不吉なこととして忌み嫌われた。 |
| 19 |
20 |
更待月(ふけまちづき)
亥中の月 (いなかのつき |
満月の五日後の月で,夜が更けないと出てこないことから。亥中月は,亥の刻の中頃(22時頃)出てくることから。 |
| 15 |
16 |
十六夜(いざよい) |
満月の翌日の月。
“いざよい”は,くずくずとためらっている様子を表す言葉。満月の翌日は,満月より月の出が遅れ,月が出るのをためらっているように見えることから。 |
| 16 |
17 |
立待月(たちまちづき) |
満月の二日後の月。
月の出を,立ったまま,まだかまだかと待っていることから。 |
| 17 |
18 |
居待月(いまちづき) |
満月の三日後の月。
月の出が遅くなるため,立ったまま待つには疲れてしまい,家の中で座って待つことから。 |
| 18 |
19 |
寝待月(ねまちづき)
臥待月(ふしまちづき) |
満月の四日後の月。
月が出るのが遅くなって,寝て待たなくては出てこないことから |
| 19 |
20 |
更待月(ふけまちづき)
亥中の月 (いなかのつき |
満月の五日後の月で,夜が更けないと出てこないことから。亥中月は,亥の刻の中頃(22時頃)出てくることから。 |
| 22.5 |
23 |
二十三夜
(にじゅうさんや) |
下弦の月。真夜中に出てくるこの月は、
月待ち信仰の対象だった。 |
| 26 |
|
二十六夜
(にじゅうろくや) |
三日月を反転させた形の月。
午前3時頃昇り,月待ち信仰において重視された対象だった |
| 満月以降 |
|
有明の月
(ありあけのつき)
残月(ざんげつ)
残んの月 |
朝になっても沈まず残っている月。 |
| 28以降 |
|
晦日の月
(みそかのつき) |
“晦日”(三十日)とはその月の最後の日のことで,新月が近くなり出てこない月のこと。転じて,あり得ないことを例えて言う。 |
| ー |
|
雨夜の月
(あまよのつき) |
見ることのできない雨の夜の月のこと。転じて,存在するのに見えないものを例えて言う。 |
| ー |
|
昼の月
(ひるのつき) |
昼間に薄く見えている月のこと。転じて,見えているけど存在感が薄いものを例えて言う。 |
 |
 |
 |
 |